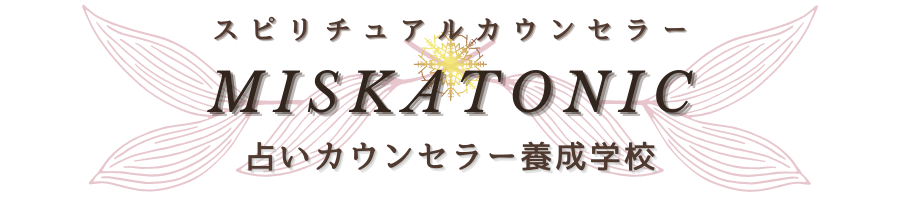クライアントに寄り添う占い師・占いカウンセラーの皆様
こんにちは!
占い師の集客とリピートを応援する
占いカウンセラー、スピリチュアルカウンセラー養成講師、
スピリチュアルビジネスコンサルタントの
ミスカトニックです
さて、オセロ中島騒動ネタもこれで4回目の連載ですね。
あまり連載物ばかりも、正直どうかと思っています。
ただ、謎に満ちた(?)心理カウンセラーのお仕事を垣間見ていただければ。
最近では心理学を学ばれている占い師やセラピストの方も多いので。
また、共依存や依存などの渦中にいるクライエントにどのように対応するかという参考になれば幸いです。
では、まいりましょう!
【『悪魔の使徒』という役割】
オセロ中島さんの件もそうですが、問題行動のあるクライエントに対して第三者がいきなり介入して解決を図っても、効果は限定的です。
多くの場合、反発をされてさらに状況を悪化させるだけです。
特に、対象がカルト(と呼ばれる宗教)や共依存の場合、その依存対象の中に自分の存在意義を見出しているため、より困難です。
なぜなら、周囲の反対はより共依存を強化することもあるからです。
暴力をふるう夫について「いや、違うの。あの人は悪くなくて、あの人を理解しきれない私や社会が悪いの」
というケースは結構あるわけです。
そうした人に離婚を迫っても、「私が守らなきゃ!」となるのがオチです。
さて、皆さんはこうした方を愚かだと思いますか?
自業自得ですか?
私はそうは思いません。
なぜなら、その人にとっては、それが真実なのですから。
真実とは、結局のところ「私たちが信じること、信じないこと」で構成されています。
そして、何を信じて何を信じないかは、その人の自由ですよね。
だから、基本的に私たちはそこには立ち入れません。
しかし、客観的に考えて問題がある場合は介入が必要になります。
ここにはジレンマがあるのですが、このジレンマを解消する方法はないのでしょうか?
よく私はコンサルタントとして「悪魔の使徒(devil’s advocate)」という方法を用います。
これは、あえて相手に対して反対意見をいう事で、相手が持つ主張の正しさを検討するものです。
特に問題点の洗い出しの場合は、よくこれをしますよね。
「あなたのビジネスモデルはよく分かった。
だけれでも、問題がないか改めて検討する必要がある。
だから、私は『devil’s advocate』をしてみるよ」
という具合ですよね。
実は、これと似たカウンセリングの技法はちゃんとあります(名前はど忘れしましたが)。
ただし、この技法を使うには条件があります。
治療構造が明確であり、かつ相手の同意があり、転移や逆転移の心配がない…などなど。
ただ、この技法を心理カウンセリングで用いる場合、本当に神経を使います。
と言うのは、一歩間違えると相手に対する批判にしかならないからです。
だから、用いる場面は限定されているのですが、しかし条件さえ整えば、効果的な技法です。
特に健全な社会性を喪失したクライエントには、検討するべき技法です。
…絶対に慎重に!ですが。
【非難か検証か】
いうまでもありませんが、私たちはクライエントの心を扱います。
それはスピリチュアルでも心理カウンセラーでも同じです。
そして、心を扱うということは、大なり小なりクライエントの「信じていること・信じていないこと」と対峙することを意味します。
「みんな、私のことを嫌っている気がするんです」
「彼は暴力をふるうけど、本当は良い人なんです」
「人前に出るのが怖くて仕方がないんです」
これは全てクライエントの「信じていること・信じていないこと」から構成されています。
ここを非難することはカンタンです。
また感情的には非難したくなる気持ちも、よく分かります。
ただ、ここを非難して相手が改まってくれたら、話はカンタンです。
時に人は叱られることも必要でしょう。
ただ、そうでない場合、非難は私たちとクライエントとの繋がりを断ち切るだけでなく、クライエントの状況をさらに悪化させます。
だから、私が皆さんに提案したいのは…
「一緒に検証する」
という態度であり姿勢です。
感情論的な非難や批判は少し脇に置いて、まずは検証しませんか?
相手がどれだけ愚かしいことを信じていても、その人にとってはそれが当然のことなのです。
ただ、そこには未知なる部分もあるでしょうし、盲点もきっとあるでしょう。そこを一緒に検討して見つけていくのです。
表面的にクライエントの感情に合わせることが「寄り添う事」ではありません。
そこを一緒に考えるという姿勢が、「クライエントに寄り添う」という事ではないかと思います。
…さて、こうしたマインドコントロールに関するネタはたくさんあるのですが、ひとまずは、これで終わりとしましょう。